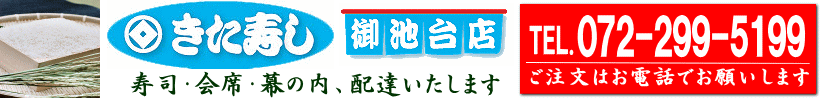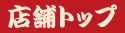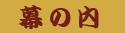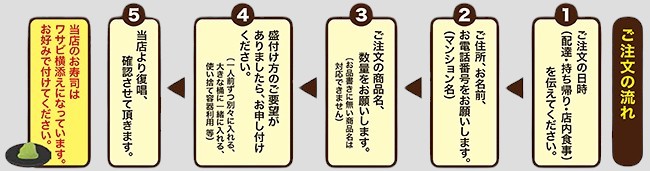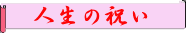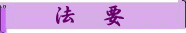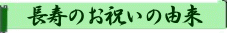|

 
|
| ◆◆◆ きた寿司 からのお知らせ ◆◆◆ |
|
寿し・会席・幕の内 配達します!
☆土・日・祝日は混み合います。お早目にご予約ください。
☆泉北ニュータウンとその近隣・和泉市光明台・みずき台
(その他のエリアはご相談ください)
☆ご注文2,800円より配達いたします。配達料無料。
|
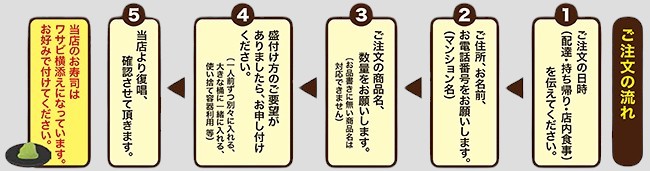
創業、昭和48年、泉北ニュータウン開発当初からのお店です。
現在は、寿し及び仕出し料理専門店として、ご好評いただいております。
お客様のご家庭でのお慶びの日や、仏事のお席、又会合でのお食事にご用命下さい。 |
|
住所
|
堺市南区御池台3-1-8
|
|
電話番号
|
072−299−5199
|
|
配達時間
|
10時30分〜18時30分(配達受付 9時〜18時30分)
※品切れの場合、早じまいすることがあります。
|
|
定休日
|
月曜日・火曜日・元旦 (定休日が祝日・お盆・年末年始は営業します)
|
|
配達エリア
|
泉北ニュータウンとその近隣、和泉市光明台・みづき台
(その他のエリアはご相談ください)
ご注文 2,800円より配達いたします。
|
|
◆御結納・御婚礼及び、仏事料理等の御相談にも応じます。お気軽にご相談ください。
◆11月下旬よりおせち料理も承ります。
|
|
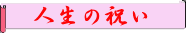
| ●出産祝 |
|
|
出産の内祝いはお宮参りの日に、奉書を八つ切りにした紙に「内祝」と書き、下に赤ちゃんの名前を書いて品物の上に添付する。 |
| ●お宮参り |
|
|
お宮参りとは、子供が生まれてから初めて産土の神にお参りすることを言い、土地の氏神様に参詣する。
お宮参りの日は男女によってちがうが、男児は出生の日から数えて三十一日目、女児は三十二日目にお参りすることが多い。 |
| ●七五三 |
|
|
十一月十五日を「七五三」といい、数え年、男児は三歳と五歳に、女児は三歳と七歳にお宮参りをして、祝うことがしきたりとされている。祖父母や近い親戚は、内祝いの膳に招いてお礼に代える。 |
| ●結納 |
|
|
結納の取り交わしは、吉日の午前中に行ないます。ただ、めでたいことですから、夜にかからぬよう午前中にすませるのが理想的です。 結納の受け渡しが終わったら、使者に祝膳を出すか、もしくは金包を渡します。 |
| ●荷入れ |
|
|
荷物送りは結婚式の約一週間前にすればよい。荷宰領・荷役・運転手の人にも祝い膳又は茶菓などでもてなし、「酒肴料」又は「祝儀」を包む。「荷物目録」を添えて届け、店から直送する荷物は日を決めて届けるように指示する。 |
|
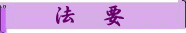
| ●一周忌までの法要 |
|
| 初七日 ・・・・・・・・ |
6日目 |
| ニ七日 ・・・・・・・・ |
13日目 |
| 三七日 ・・・・・・・・ |
20日目 |
| 四七日 ・・・・・・・・ |
27日目 |
| 五七日 ・・・・・・・・ |
34日目 |
| 七七日 ・・・・・・・・ |
49日目 |
| 百ヶ日 ・・・・・・・・ |
99日目 |
| 初盆(新盆) |
|
|
| ●年忌法要 |
|
| 一周忌 ・・・・・・・・・ |
翌年 |
| 三回忌 ・・・・・・・・・ |
2年目 |
| 七回忌 ・・・・・・・・・ |
6年目 |
| 十三回忌 ・・・・・・・・ |
12年目 |
| 十七回忌 ・・・・・・・・ |
16年目 |
| 二十三回忌 ・・・・・・・ |
22年目 |
| 二十七回忌 ・・・・・・・ |
26年目 |
| 三十三回忌 ・・・・・・・ |
32年目 |
| 三十七回忌 ・・・・・・・ |
36年目 |
| 五十回忌 ・・・・・・・・ |
49年目 |
| 百回忌 ・・・・・・・・・ |
99年目 |
|
| ●新盆には棚経をあげる |
|
新盆には、親戚や親しい知友を招いて供養し、菩提寺から僧侶を招いて棚経をあげる。僧侶にはお布施を包む。 |
| ●忌日と忌明けの法要はどのようにするか |
|
忌日には冥福を祈り、僧侶の読経をして法要を営む。特に初七日の法要は僧侶の読経、法要の後、出席者には茶菓子や精進料理で接待する。また、四十九日には忌日がおわり、忌明けの法要を営む。 |
|
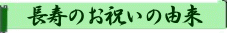
| 長寿を祝う習慣は奈良時代に始まりました。ところで、長寿を祝う言葉が還暦以外にもいろいろありますね。古稀をはじめ、喜寿、傘寿、米寿など。現在は誕生日に祝うのが一般的のようですが、昔は数え年の節句やおめでたい日に祝うしきたりでした。
|
| ●還暦<かんれき>(60歳) |
|
|
昔は1年ごとに干支の名前がついていたとされてます。その種類は十干と十二支を組み合わせた60種類で、それを一めぐりと考えました。60年で暦が元に戻ることから還暦というようになりました。 |
| ●古稀<こき>(70歳) |
|
|
中国の唐代の詩人、杜甫の「曲江」の詩に「人生七十古来稀也」という句があることから名づけられました。 |
| ●喜寿<きじゅ>(77歳) |
|
|
「喜」という字の草書体が、七十七と読まれることから由来します。 |
| ●傘寿<さんじゅ>(80歳) |
|
|
いわれは「傘」の略字が八十とも読めるからです。 |
| ●米寿<べいじゅ>(88歳) |
|
|
「米」の文字を離して書くと八十八になると言い伝えられています。 |
| ●卒寿<そつじゅ>(90歳) |
|
|
「卒」の略字が「卆」、離して書くと九十になることが元です。 |
| ●白寿<はくじゅ>(99歳) |
|
|
九十九歳は百歳まであと一歳。「百」という文字から一(イチ)をとると「白」になることが理由です。 |
|